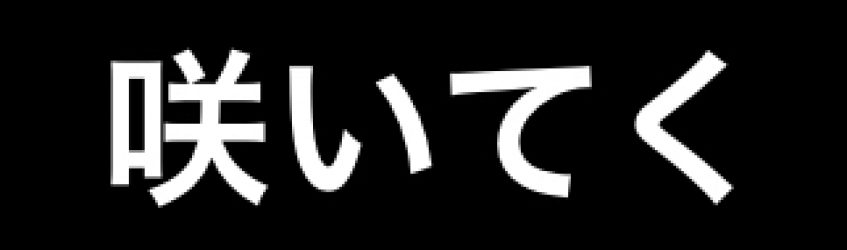それぞれ有名な産地としては、
天然林
◆ 青森県の青森檜葉林(ヒノキアスナロ林)
◆ 秋田県の秋田杉林
◆ 長野県の木曽檜林(ヒノキ林)
これらが天然林の三大美林と言われるところです。
人工林
◆ 静岡県の天龍杉林
◆ 奈良県の吉野杉林
◆ 三重県の尾鷲檜林(尾鷲ヒノキ林)
これれは人工林の三大美林と言われています。
この中のいくつかは聞いたことがあると思います。
“木曽の檜“なんかは銘木の一級品なので、殆どの人は一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
天然林と人工林の違いについて
天然林は、自然のままの植生を利用して、利用できそうな樹木を選んで伐採する択伐(たくばつ)という伐採方法をとっています。
自然のままの状態で、人間が利用する樹木の他に広葉樹や低木類が混合して存在します。
当然に、多くの生物が生存する自然そのものの森です。
一方、人工林は、一般的に利用目的の樹木を植樹するためにもともと茂っていた斜面一帯の樹木を伐採します。自然の守りを消し去った上で目的の樹木を植栽し、それ以外の樹木や草本などが生えるのを抑えるために定期的に刈払いを行います。
単一の樹々の森が出来上がります。
植栽を行った後の30年〜50年後に全ての樹を伐採して斜面を丸裸にした後、再び幼木を植樹する皆伐(かいばつ)を繰り返します。
この目的は、効率よく樹木が育つ様にしたり、効率よく一連の伐採作業を行える様にするものです。
天然林・人工林それぞれの特徴について
天然林の森は、自然の森ですので生物多様性に優れます。
広葉樹も多く生息しているため、多くのバイオマスを含んだ用土が堆積して多くの微生物が生息しています。
生産する木材は均一とは言えません。
基本自然の樹木ですので枝が多く大きな節が目立ちます。
著名な木曽檜の木材には大きな節があるのはこのためです。
一方、人工林は目指すのがひとつの種類の樹木である単一林です。
単一林は樹林内の土が偏ります。
バイオマスを含んだ用土は限られ土壌の微生物も少なくなるのは必然です。
水分を保てない土壌は豪雨などの際に一気に下流域へ流れ出し、土砂災害などを引き起こすこともあります。
また、偏った生物が棲みつき結局樹木に危害を与えます。
ネズミの被害は大きく、阻止するために殺鼠剤を撒いたりする行為はさらに複雑に生物多様性に影響を及ぼします。
生産する樹木は植える時期が一定で、単一品種であるため生長が均一です。
商品としての木材は安定した価格が見込まれるということはあるようです。
立派な吉野杉や尾鷲檜には無節が多く、四方柾と言われる銘木の産地であるのはこの様なことも関係しているのです。
さて、皆様はどちらの樹木を選ぶでしょうか?